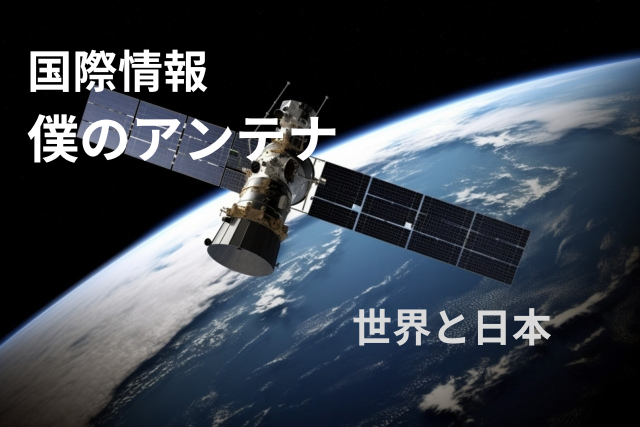2026年2月、中東情勢はかつてない臨界点に達している。トランプ政権による核開発停止の最後通牒、そしてペルシャ湾への米空母打撃群の集結。専門家が予測する米軍の攻撃確率は65%に達し、一触即発の事態だ。
ここで問われるのは、「米国は空爆による短期決戦(約3カ月)で、イランを屈服させられるのか」という点である。
非対称戦の脅威と「経済的封鎖」
戦火が開かれれば、イランは正面衝突を避け、ホルムズ海峡での「非対称戦」を展開するだろう。機雷、高速艇、自爆型ドローン。これらに米艦隊を全滅させる力はない。しかし、海上保険料を暴騰させ、世界のエネルギー市場を麻痺させるには十分だ。原油の9割を中東に依存する日本にとって、これは文字通りの「生命線の断絶」を意味する。
「空爆のみ」が招く権力の空白
米国の戦略は、地上軍を送らない「リスク限定型」の破壊工作になるとみられる。だが、ここには大きな落とし穴がある。2003年のイラク戦争の教訓だ。
体制の結束: 外部からの攻撃は、皮肉にもイラン国内の保守派を結束させる。民主化運動を「外患」として圧殺する口実を与えかねない。
制御不能な混乱: 空爆で指導部を叩いたとしても、その後の統治計画(Day After)がなければ、強大な「革命防衛隊」が軍事独裁を強めるか、あるいは国全体がシリアのような泥沼の内戦に突入するリスクがある。
独立250周年の祝祭か、自爆か
2026年7月の独立250周年、そして11月の中間選挙を控えた政権にとって、原油高騰を招く軍事行動は一見「自爆」に見える。しかし、政権はこれを「長期的安定のための先行投資」と正当化するだろう。イランという不安定要因を根絶することこそが、米国の覇権を盤石にすると主張するはずだ。
世界が見届けるのは、強いアメリカの復活を賭けた「究極の勝負」か、それとも歴史に学ばない「最悪の再演」か。世界経済と平和の分岐点は、まさに今、この瞬間にある。