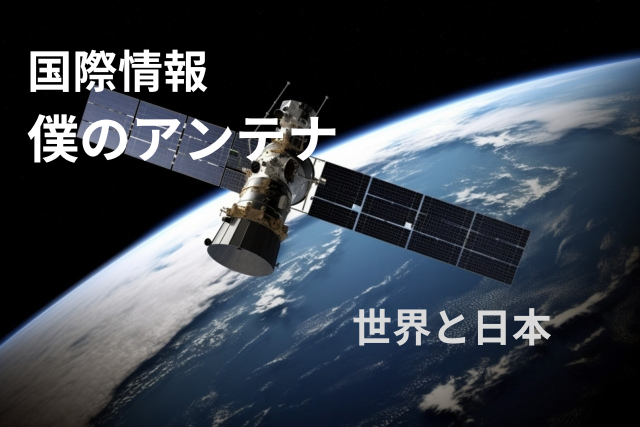石破氏がトランプ大統領との会談を終え、帰国してきた。国内の評価は概ね良いようだ。率直に言えば、よほど期待値が低かったからだと思わざるを得ない。
テレビ映像で伝わってきた石破氏の所作は最悪であった。カメラと記者たちが入っている前での椅子の座り方、姿勢、握手のしかたなど、国際舞台に不慣れなことが120%出ていた。英語などブロークンでもかまわない。重要なことは、相手と同じ平面上に存在し、できる限りバリアなく会話ができる人間だと相手に感じてもらうことだ。今回は、トランプ氏は石破氏に気をつかい、褒めちぎっていたことに救われてはいる。今後、首相の役割を続けていくとお考えなら、この辺の儀礼的なことは改善していただきたいものだ。
トランプ氏が石破氏を丁寧に扱ったのにはいくつか理由があるだろう。一番の理由は、トランプ政権の政策優先順位だと考える。現政権の通商政策上の仮想敵国は何といっても中国だ。この中国を包囲し、迂回ルートを塞ぐ意味で対カナダ、対メキシコの関税を発動している。また、これからモディ首相も訪米するようだが、インドとの通商課題も大きい。こうした中では、日本との交渉は、仮に将来的にあるとしても、戦略的優先順位が低いのだ。今は味方として丁重に扱うのが米国の利益だ。
今回の首脳会議の成果としてまとめられた共同声明を見ると、石破氏はまず安全保障の枠組みの確認を行ったことがわかる。日米安保の確認と第5条が尖閣諸島を含むことを改めて文書化した。既定の路線を再確認したもので、対中国への姿勢を考えれば、両国にとってこれ以外で有効な選択肢は見当たらないのだから、当然のことであり、外交的「成果」とは到底呼べないだろう。
経済・産業の分野を見ると、ふんわりとした総論が述べられているだけで、何も用意がなかったことがわかる。国際宇宙ステーションやアルテミス計画に従来路線で参加すると言っているのだから、ロケット・宇宙機器分野に日本が誇る精密加工技術や微細加工技術を動員し、宇宙産業のリーダーシップを共に取っていこう!くらいの風呂敷は広げてほしかった。大統領就任式の翌日、ラリー・エリソン氏、サム・アルトマン氏と並んでAI分野の巨大投資をぶち上げた孫正義を少しは見習ってほしいものだ。
筆者が注目したのは、アラスカで産出が期待される天然ガスの供給を受ける話だ。エネルギーの中東依存度を下げることは、安全保障上のリスクをさげることにもつながる。日本にとってはとても良い話に見える。日本の発電の約30%は天然ガスを使っており、世界的に見ても天然ガスをうまく利用している部類に入る国だ。LNG関連の港湾インフラの増強や輸送航路整備で世界の手本になるようなものを一緒に作ろうなどと言えたはずだ。
なお、筆者が驚いたのは、日本製鉄のUSスチール買収案件だ。初めて会いに行って、トランプ氏が一緒に沈んだ船を引き上げてくれるとでも考えたのだろうか?この買収話は、2024年選挙イヤー前から持ち出したことが最大の敗因だろう。共和党と民主党の大接戦の中で、得票の観点からは、どちらの政治勢力も賛成しないことが最善策となる。政治的に「詰み」となった事案であり、大量の鉄鋼輸入を確約でもしない限り、トランプ氏は翻意して支持するはずがないのだ。
石破氏や現政権は、通商、産業、エネルギー政策を従来の枠組みからしか考えていないと予想してきたが、それこそをまさに今、大きく発想転換する時に来ている。約30年ほど続いてきたグローバル自由貿易の時代ははっきりと終焉した。リベラルな方向に振れすぎた国際機関(国連とその専門機関など)の機能不全や非効率も露わになってきた。こうした環境の中では、政治と産業が密に連携して、新たな秩序での国益を取りに行くことが重要だ。残念ながら、日本はそうできる環境にありながら、できていない。
石破氏は「地方創生 2.0」を説いている。約10年やってきた地方創生だが、ぼんやりした話で成果は見えない。ふるさと納税に関わる業者や地方に交付されるプロジェクト支出に関わる業者が「さや抜き」し、何か将来へのプラスが積み重なっている感じはしない。地方における産業政策が不在だからだ。こんなことを続けていては、失われた30年がさらに伸びて40年、50年になりかねない。
昨年末からの米価の急騰に対しても政権の反応は鈍い。石破氏はそもそも農林族だ。米価の高騰はどうやらJAと農水省の合作である可能性が高い(山下一仁氏論考)。国民の主食の高騰、ガソリン価格の高止まり、エネルギー戦略の欠如、産業政策の不在、挙げればきりがない。石破氏が経済オンチだと思う理由は、このようなことにある。