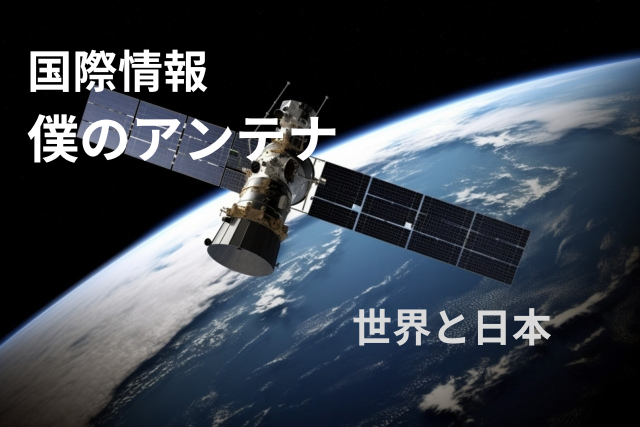7月23日トランプ氏の投稿で日本に伝わった15%の関税で株式市場は2日間の熱狂を続けている。不確実性がなくなったからという理屈はあるが、筆者にはどうも腹落ちしない。むしろ関税率ばかりに注目した反応には、大きな落とし穴があると感じている。
自動車産業は、ある程度の国際競争力を保ち、産業のすそ野も広大な基幹製造業であることは間違いない。これまでの関税2.5%が15%になるのだから、25%よりはマシとは言え、短期的な痛みが出ることも間違いない。米国市場でのマーケティング戦略や製造拠点戦略レベルでの対応が求められるだろう。また、米国以外の市場の強化もより力を入れることになろう。日産はもっと苦しくなるだろうが、トヨタ、ホンダあたりは、既にいくつものシナリオを準備していただろうから、前提が見えてきたところで粛々と手を打ち始めることだろう。自助努力で生き残れる可能性は充分ある。
赤沢大臣によれば任務完了とのことだ。EUやインド、中国が25%で日本だけが「交渉」によって15%なのだとしたら、確かに任務完了かもしれない。ところが、日本も西側同盟の主要各国との横並びの扱いだとすれば、さしたる「完了」でもなかろう。トランプ氏が決裁して、交渉終了となっただけだ。
筆者が一番がっかりする点は、「合意」の付帯事項の中の5,500億ドル、日本円で約80兆円の米国への投資だ。ホワイトハウスのサイトには発表されているが、日本政府側での取り扱いは今のところ不明瞭だ。
日本全体の設備投資額が年間約100兆円強の規模だ。これに比すれば80兆円の規模感はお分かりだろう。昨年決まった半導体製造ラピダス社への政府出資でさえ1,000億円であり、それからしても二ケタ違いの金額だ。問題は、このような規模の投資だとすれば、まずもって日本の産業も同時に発展するプロジェクトとか、事件・事故が出始めているインフラの整備とかに使われてこそ国益ではないか?という点だ。米国側の発表内容によいれば、お人よしの日本は多額の投資を行い、米国産業を振興することになったというトーンで書かれている。
まったくお寒い話に過ぎない。なるべく既存政策の変更なしに、トランプ禍をどうにかやり過ごしたという風に受け止めざるを得ない。まずます貧しくなり、在日米軍の自由出撃権や地位協定を80年見直すこともなく、永久敗戦のまま安全だと自分たちに言い聞かせて生きていくことが「国益」だと考えるなら、これも仕方あるまい。
支払う気のない手形を切ったのならそれでも良い。次世代の分野で製造業を取り戻すとか、エネルギー政策や農業・食料安全保障政策を大きく見直すとか、人口減少に対する大きな戦略を描くなどしなければ、「国益」は見えてこない。現政権ではまったくもって微塵も考えてもいないことがありありと見えてくる日米交渉だったと感じる。